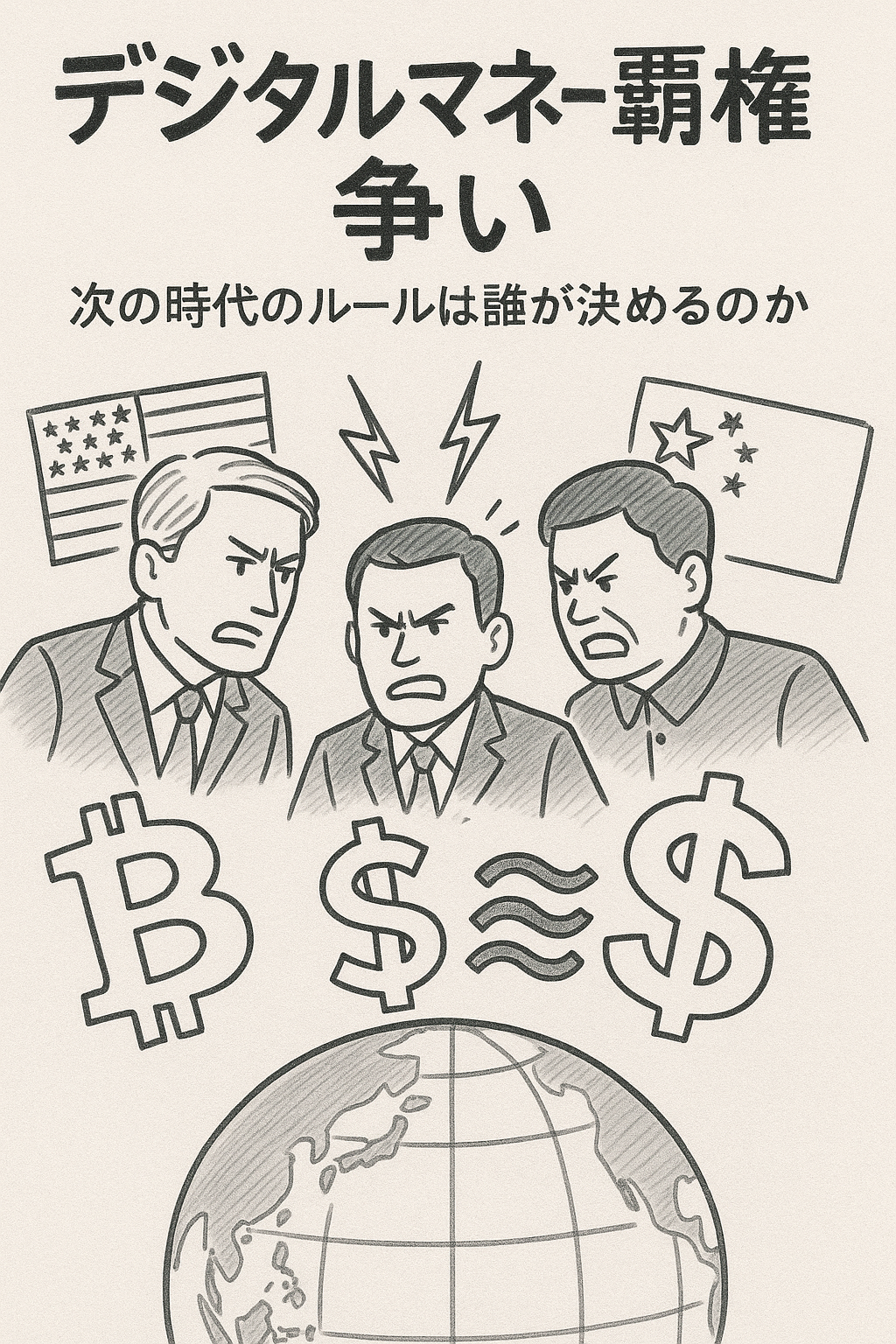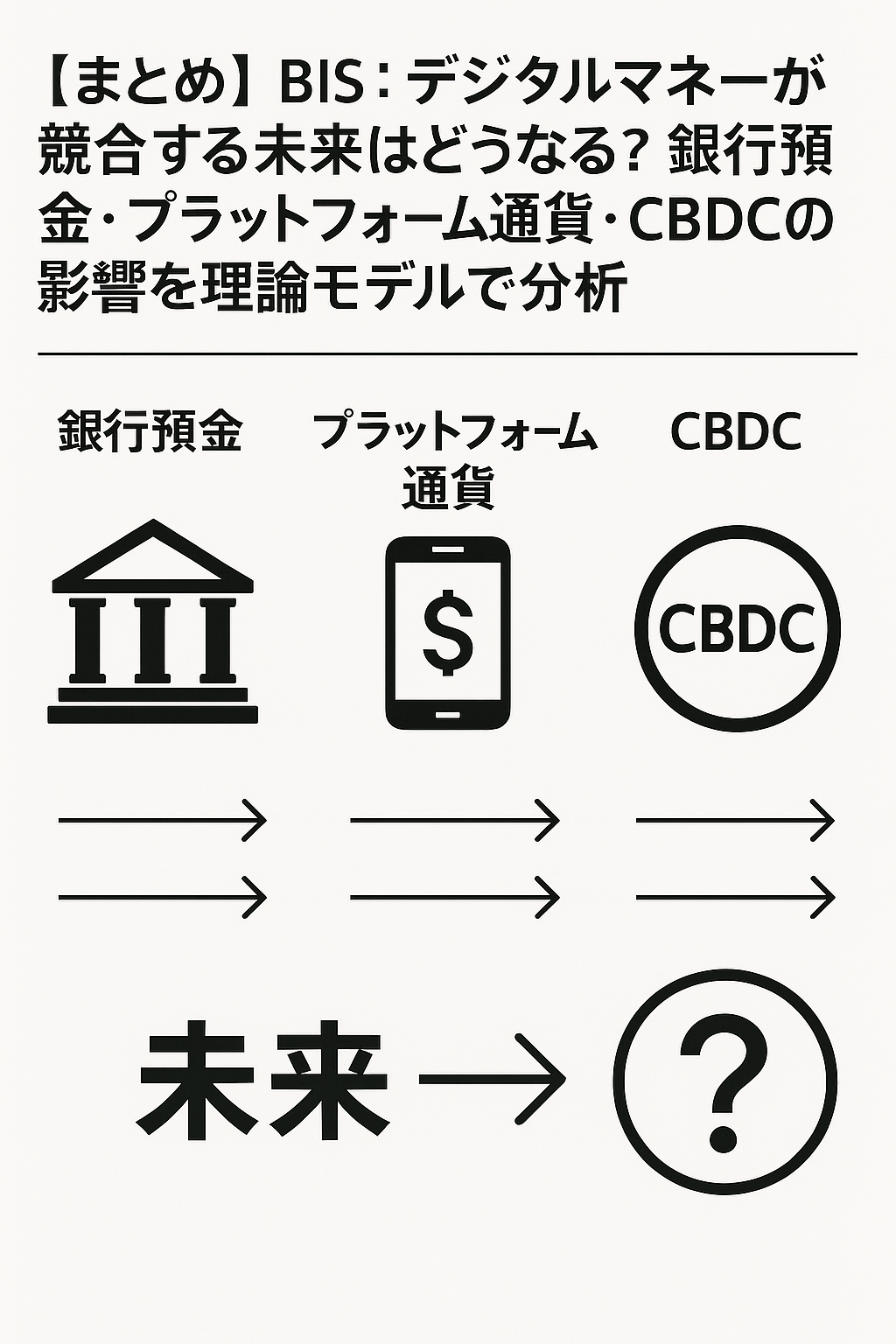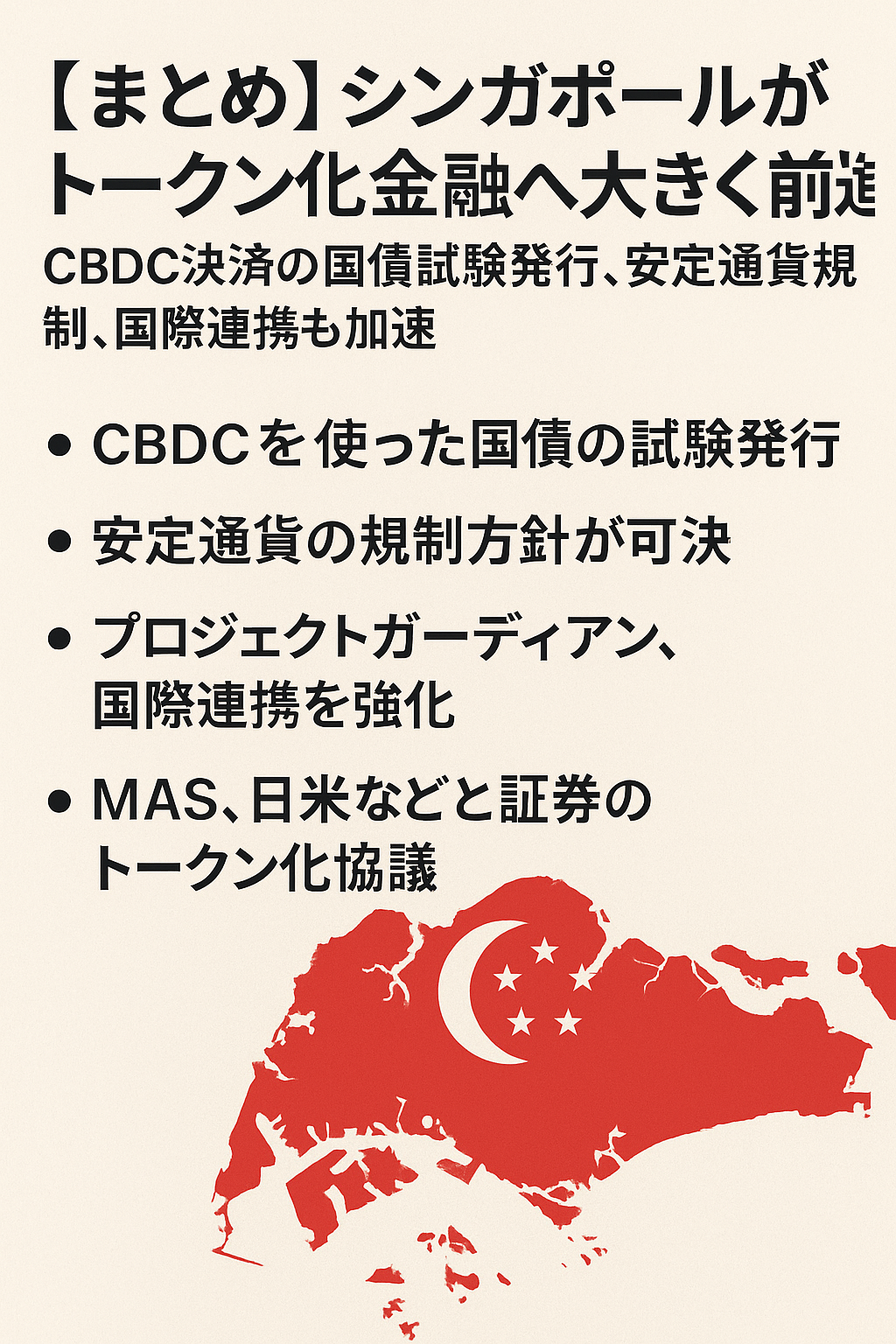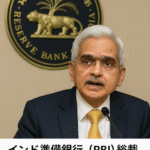デジタルマネー覇権争い:次の時代のルールは誰が決めるのか
1. 背景
- 8十年以上、米ドルは世界金融の基軸通貨として信頼と安定を提供してきた。
- デジタル通貨の台頭により、国境を越えた送金がより速く・安く・既存システム外で可能になりつつある。
- 中国は国家主導のデジタル人民元(e-CNY)でドルの優位性に挑戦。
- 米国はドル連動型ステーブルコインで影響力を維持しているが、CBDC開発は遅れ気味。
2. 中国の動き
- 取引規模:2025年6月時点で累計7.3兆ドル以上、29都市以上で利用。給与や交通運賃、EC決済にも対応。
- 国際戦略:
- mBridge(香港・タイ・UAEと共同)で数秒・低コストの国際決済を目指す。
- 上海に国際e-CNY運営センター開設。
- 独自SWIFT代替システムを構築し、西側制裁回避の手段としても活用可能。
- 課題:国内では依然としてWeChat PayやAlipayが優勢で、国際需要は限定的。
3. 米国の現状
- デジタルドルは未発行。FRBは国内改善を重視し慎重姿勢。
- 2025年のトランプ大統領令でCBDC禁止が政治的障害に。
- 民間主導のUSDC・USDTなどが「市場型デジタルドル」として拡大。
- 2024年のステーブルコイン送金額は27.6兆ドルでVisa+Mastercard合計を上回る。
- 2028年までに時価総額5,000億ドルに達する予測(J.P.モルガン)。
- 課題:規制が緩く、犯罪や不正利用との関連も指摘。
4. CBDCとステーブルコインの違い・影響
- CBDC:政府保証付きで、国家がマネーアーキテクチャに直接関与。設計次第で匿名性も可能だが、民主的監視が不可欠。
- ステーブルコイン:民間発行でドル資産に裏付けられ、国際的ドル流通を促進。ただし規制不足のリスクあり。
- 中国のCBDC優位が続けば、国際金融ルールを自国仕様に作り替える可能性。
5. 将来の展望とリスク
- e-CNYの国際決済採用が進めば、ドル基軸体制や米国の制裁・借入コスト・影響力が低下。
- 米国がデジタル通貨技術開発で後れを取れば、将来の「マネーのルール」が北京で決まる危険。
- 将来の金融システムはCBDC・ステーブルコイン・従来通貨が共存する可能性が高く、米国は両方に投資し、国際ルール形成で主導権を握るべき。